
教員にきく:三島 武之介(国際政治論、政治社会学)
教員にきく
2018.07.28
「先人たちの歩みに学び、希望ある未来をつかめ」
三島 武之介(みしま たけのすけ)准教授にロ ングインタビューを行いました。
専門分野・研究テーマは何ですか?
国際政治論、政治社会学です。イギリス政治外交史からこの道に入りましたが、大学院でアメリカ政治外交史に転じました。主として、アメリカを世界大国に造りかえた指導者たちのコミュニティ形成を研究しています。
研究の動機は何ですか?

アメリカに遊学した際、私たちと同じ「ふつう」の人々が、国際政治に関心をほとんど持っていないことに驚きました。「アメリカは世界大国なのに、なぜ興味がないの?」と。その強烈な印象が脳裏に焼き付いて離れず、優秀な学友たちが母校を巣立った後も長い間、居残り続けるハメになりました(笑)。
私たちも目にできる研究成果はありますか?
もしあるとしたら、『「アメリカの世紀」を興したリーダーたち―グローバル化に向けた国家改革』(松籟社、2016)ぐらいでしょうか。学術雑誌に限られますが、幸いなことに優れた書評もいただいています。
書き上げるまでに、苦労はありましたか?
大ありです(笑)。
私の研究対象にあたる人々は「エスタブリッシュメント」と呼ばれ、ごく平凡なサラリーマン家庭に育った私とは全く境遇が異なっていましたから、彼らのことを調べるのはものすごく骨が折れました。
それ以上に、執筆当時は、生計を立てるために高校教員をしていましたから、研究に割ける時間は絶望的に少なかったんです。博士論文の主査だった先生の励ましがなかったら、研究そのものもやめていたかもしれません。
大学で良い先生に恵まれたんですね。
ええ。先生は素晴らしい教育者でした。
ただ、先生との縁は、先生の下で学んでいた先輩と知り合ったことに始まっているんです。その出会いも同期からの紹介がきっかけでした。つまり、学友にも恵まれていたのです。
JIUの学生たちにも、先生や学友との絆を育んでもらいたいですね。

明治記念館での結婚披露宴後、同窓の学友たちに胴上げされる三島准教授
学生時代は面白かったみたいですね。
そうですね。苦労も多かったのですけれど、恵まれた学生生活を送りました。
母校には高名な先生方もたくさんいましたが、私たちの相手をよくしてくれました。学部生の頃、同期と食事に行った帰りに思いつきで、ゼミの先生のご自宅に「今から遊びに行ってもいいですか」と電話しても怒られませんでした(笑)。
街の方々も寛容で、大事にしてもらえました。皿洗いさえすれば、タダでお腹いっぱい食べられる中華料理のお店もありました。住んでいたアパートの大家さんも、家庭菜園でとれた野菜やお中元のビールを分けてくれました。
研究以外にハマっていたことはありますか?

先人たちが残した文化遺産を味わっていましたね。
私が学生時代を過ごした京都は、幸いにもアメリカによる原爆投下の第一目標から外されましたので、戦争の被害をさほど受けることがありませんでした。おかげで、古くからの建造物や美術品が数多く残りました。
悠久の時を刻んできた文化に囲まれて暮らしてみたいというのが、東京ではなくて京都の大学に進学しようと思った大きな理由の一つです。

とくに好きだったのは、自転車(ロードレーサー)で神社・仏閣を巡ることです。
趣味が高じてくると、奈良の吉水神社とか、滋賀の多賀大社とかまで、遠出するようになりました。実は、千葉県内で最初に降り立った場所も香取神宮なんです(笑)。
国際交流学科の学生については、どう思われますか?
進んで人と関わろうとする学生が多いことに感心しています。アドバイジーでない学生も研究室によく来てくれます。留学や進路の相談もありますが、「試しに来てみた」「暇だった」という人もいます(笑)。
思い出話ですが、私の着任と同時に入学した2018年度入学生の中には「同期の顔を見に来た」という人もいました(笑)。この人懐っこさも、うちの学生の大きな特徴ですね。とても良い傾向だと思います。
国際交流学科の先生方についてはどうですか?
尊敬できる方が多いですね。どの先生も立派な研究業績をお持ちですが、教育熱心で、学生と親しくしています。教員と学生の距離はとても近くて、談笑している姿をよく見かけます。
先日も、Walt Disney World Resort Internshipに向けての面接指導をされている先生を見かけましたね。実を言えば、若手教員の私も、分からないことは先輩教員に教えてもらっています(笑)。この場を借りてお礼申し上げます。
大学ではどんなことを教えていますか?
担当科目は教員紹介にある通りですが、どの講義・演習でも、現代を生きる我々を取り巻く政治・経済のあり方がどのようにして出来上がってきたのか、を学生たちと共に考えています。
「鉄血宰相」と呼ばれ、ドイツ統一を成し遂げたビスマルクが、「愚者だけが自分の経験から学ぶと信じている。私はむしろ、最初から自分の誤りを避けるため、他人の経験から学ぶのを好む」という有名な言葉を遺しています。
学生にも、より良い明日を生きるために、先人たちの歩みから多くの教訓を得てもらいたいですね。
授業で心がけておられることはありますか?
いま話題になっている出来事について、自分で調べる力を養うことを大事にしています。
具体例を1つだけ挙げますと、「国際関係論」の講義にて、第二次大戦後の自由貿易体制を取り上げた際に、「トランプ 貿易 関税」などの関連するキーワードをスマホで検索して、アメリカによる保護貿易への傾斜、それに対する日本や西欧の懸念などを調べてもらいました。
調べる作業を重視するのはなぜですか?
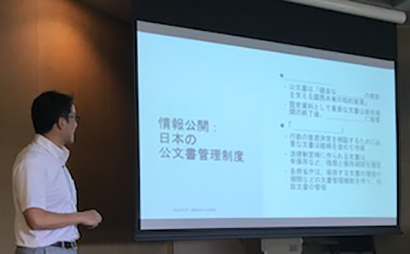
世界に関心を持ち、情報を求め、それにアクセスできる力こそ、「世界で通用する人材」の第一歩だと考えているからです。
先日、日本語教員を目指す学生が国際ニュースを見るようになった、と教えてくれました。たとえ専門外の講義であっても、授業内容が「世界を知る」ことにつながっていると体感できる学生がいてくれることに、深く感謝しています。
これから国際交流学科に入りたいという学生に一言お願いします。

あなた方は、世界史的転換点に立っています。人間のもつ価値そのものの意味が変わり、それに応じてあなた方の価値観も大きく変わっていくでしょう。こうしたパラダイムシフトの時代にあって幸せになるためには、目の前に見えている「いま」を相対化し、変化の荒波に振り回されない価値観をつくらなければなりません。
国際交流学科は、まさにそうした価値観をつくる機会を提供しています。語学を学んで、その土地の事物に触れ、人々と語り合う。そうして海外で体験してきたことを、講義や演習にて言葉などで表現するスキルを身につける。教員や仲間たちと対話しながら、考えをさらに深めていく。このプロセスを繰り返していく中で、あなた方の価値観は堅固なものに近づいていきます。
確かな価値観をもち、価値を語ることのできる人材が、これからの社会で求められる人材像だと思います。そのような人材になるための準備ができること、これこそが、就職を4年遅らせてでも国際交流学科で学ぶ理由だと私は考えています。知的好奇心にあふれた方のご入学をお待ちしています。
略歴
福岡県生まれ。京都大学総合人間学部卒業、京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了。学術博士。早稲田大学系属高等学校英語科主任教諭(グローバル教育担当)を経て、2018年4月より着任。研究者詳細はresearchmapをご覧ください。