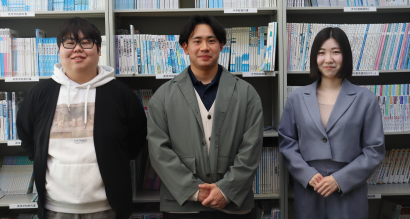【学生広報スタッフ】卒業後は教員として学びの場を支える学生を取材
学生活動
2025.03.13
私たち学生広報スタッフは、JIUの情報を学内外に学生目線で発信をしています。主に学生へのインタビューやイベントの取材を行っています。
学生広報スタッフ 川島 乙晴(国際人文学部3年)
学生広報スタッフ 宮田 光(経営情報学部3年)
今回は教職課程を履修し、教員採用試験に合格した2名にインタビューをしました。4月から中学校の教員として働く学生が過ごした学生生活や、将来の目指す姿などを伺いました。

経営情報学部総合経営学科4年 広瀬 桂さん
(北海道公立学校教員 中学校社会)
教員を志したきっかけ

中学・高校と学生生活はサッカーに打ち込んでいました。特に高校時代のサッカー部顧問の指導に大きな影響を受けました。その指導は、サッカーの技術だけでなく、礼儀やマナーを大切にするということでした。特にその顧問の先生は「義理と人情」という言葉を大切にしており、当時は厳しさに戸惑うこともありました。しかし大学生になってその指導の意味を深く理解し、自分も生徒としっかり向き合える教員になりたいと考えるようになりました。
新たな挑戦と教員への道
高校卒業後は就職か進学か悩んでいましたが、城西国際大学のサッカー部に興味を持ち、県外での新たな出会いや経験を求めて進学を決意しました。教職を取っていると他の学生より、授業数が多くなり大変な面はありました。大学では教職課程を履修、ゼミは目時先生のゼミに所属し、教員採用試験に向けて計画的に勉強を進めました。1日平均5時間の学習を継続し、参考書は某ECサイトのランキング1位のものを選んで活用しました。特に、ゼミでは過去問を解いたり、実際の先生の体験談を聞いたりする機会があり、実践的な知識を深めることができました。
目指す教員像と理想の授業
生徒との信頼関係を大切にしながら、一人ひとりの考えを尊重する授業を目指しています。生徒が自由に考察し、自発的に学びを深められる環境を作ることが理想です。また、人間性の成長も重視し、思いやりのある指導を心がけていきたいです。教員としての大変さも、もちろんありますが、生徒たちの成長の重要な時期に関われることに誇りを持ち仕事に取り組みたいです。
大学生へのアドバイス
過去に関わった先生の話を聞くことで、現場のリアルな一面を知ることができると考えています。また、勉強に不安を感じることもありますが、大学の教授や友人に相談することで解決の糸口が見つかるため、一人で抱え込まずに周りに頼ることが大切です。
国際人文学部国際交流学科4年 平山 泰我さん
(千葉県公立学校教員 中学校英語)

教員を志したきっかけ
まず自分に合う職業は何か考えた時に、真っ先に教員という職業が頭に浮かんだことがきっかけで、そこから具体的に教員について調べました。今まで教育を受けてきた先生方を思い浮かべると、仕事にやりがいを感じたり、大人になっても気持ちは若くいられたりするのは教員という職なのではないかと強く思い、教員の道に進んでいこうと考えました。
そして教科を教える先生が部活動の顧問もしているのを見て、教育現場に熱意を持っている先生に刺激を受け、自分自身も部活動の顧問をやってみたいというのも理由の1つです。中学・高校時代、得意ではなかった英語という教科にもかかわらず、英語教員を目指すという選択は、自分自身でもチャレンジでした。しかし、もし教員ではない道を目指そうとしても、違う方法で社会貢献できると感じ、英語が学べて、教職課程がある国際交流学科に入ることを決心しました。
小さいころからバスケットボールをしており、高校時代は県大会で優勝して全国大会に出場するなど、真剣に打ち込んできました。大学1年生の時から母校の中学校の部活動の外部コーチとして4年間関わってきました。もし中学校に採用された際には、4年間培ってきたものが絶対に活かせると考え、中学校の教員を第1希望に決めていました。
TOEIC は240 点から 925点に
先生からのアドバイスを受け、大学2年生の夏から4カ月アイルランドに留学し、大学3年生の冬に1ヵ月のアメリカ研修に参加しました。イギリス英語のアイルランドとアメリカ英語のアメリカでは、ディスカッションやグループワークなどアクティブな教育方法が中心で、日本とは大きく異なる方法の授業でした。この2つの留学経験のおかげで、発信できる話題が増え、教育実習の際に自分に興味を持ってくれる生徒が多くいました。
留学に行く前に受けた TOEICは 240 点と留学に行ける条件の 400 点には程遠い状態からスタートしました。まずは 400点以上を目指し、勉強に取り組んでいきました。留学から帰ってきてTOEIC を受け、スコアは一気に上がっていき、最終的に 925 点まで点数が伸びました。
教員試験対策
1次試験は英語の試験と教職教養という2つがあり、英語に関しては英検準1級レベルだといわれていて、英検の勉強はずっとしてきていたので対策はしていないに等しかったです。教職教養に関しては 約200 ページの本7冊と100 ページ近いプリント3つくらいの量をひたすら書いて読んで覚えて挑みました。短期集中型で1日2、3時間勉強して、空きコマの時間等も使い復習していました。
信頼関係を大切にする教育者としての目標
目指しているのは、生徒一人ひとりをしっかりと観察し、信頼関係を築ける教員です。自身の留学経験から、英語を「学ばせる」のではなく、「自然に使える」環境を作ることが重要だと考えています。また、大学時代のゼミ長や留学の経験から、積極的に周囲と関わりながら、相手の個性を尊重する姿勢を大切にしています。これまでの経験を活かして、生徒たちのコミュニケーション力を伸ばし、将来の可能性を広げる手助けをしていきたいと考えています。
教員を目指す学生にアドバイス
まず前提に、コミュニケーション力は必要だと思っています。さらに日常的に視野を広くして生活していくことで、教育現場に立った時も様々な生徒の実態を見られると考えていて、友達やゼミの皆と関わっていく中で、一人ひとりの性格や考えを観察して発見していくことが教育現場で生徒と関わる際も使えると思います。