
Newsletter vol.1 出版物・広報誌
城西国際大学の教育研究活動に関する情報を発信するNewsletter。毎号、全7学部共通のキーワードを軸に研究者たちの多様な取り組みを紹介します。
今号のテーマは【アフターコロナ始動】です。
マスク着用ルールの緩和に続き、5月には新型コロナの感染症法上の位置づけが「5類」に移行されるなど、「アフターコロナ」へのシフトがいよいよ本格化し始めました。この新しい社会を私たちはどう捉え、どのように行動すればよいのでしょうか。城西国際大学の研究者が、それぞれの専門領域の立場から考察・予測します。
- Highlight【保育・幼児教育】福祉総合学部 福祉総合学科 教授 倉田 新 「公私連携幼保連携型認定こども園の活用~教育・研究の場として」
- 【外国人移住者】国際人文学部 国際交流学科 教授 林 千賀 「入国制限撤廃で外国籍の子急増 日本語教育の支援急務」
- 【地域環境保全】経営情報学部 総合経営学科 教授 国武 陽子「守れ、里山の希少生物 学生のフィールド教育も再開」
- 【XR】メディア学部 メディア情報学科 教授 中嶋 正夫 「XR技術、孤立感低減するオンライン授業への活用を模索」
- 【薬剤師】薬学部 医療薬学科 助教 溝口 優 「増える外国人患者 薬剤師の窓口対応に異変も」
- 【観光開発】観光学部 観光学科 教授 多田 充 「フィールドワークで町の魅力再発見 地域振興戦略を観光協会に提案」
- 【メンタル】看護学部 看護学科 准教授 柚山 香世子 「コロナ禍で失われた触れ合い ドッグセラピーがもたらす効果に注目」
Highlight【保育・幼児教育】福祉総合学部 福祉総合学科 教授 倉田 新 「公私連携幼保連携型認定こども園の活用~教育・研究の場として」
保育をデザインすることは未来の日本をデザインすることでもあります。そうした視点で子どもにとっての最善の利益を中心に据えながら、保育を総合的に研究しています。また、大学の研究者と並行し、社会福祉法人の事務総長として14の認可保育所等を運営しながら、現場で起きるさまざまな問題について、学際的に分析し解決の糸口を探っています。
コロナ禍によって、子どもたちが接する大人の顔はマスクで覆われました。親や先生の表情を眼元だけで判断し、コミュニケーションしていたことになります。乳幼児は本来、大人の口元を見て反射的に笑いますが、マスクをした状態ではその感知力が発達しにくいのです。これがその後の言語能力の発達にどう影響してくるか、これからの研究で明らかになっていくでしょう。
千葉県東金市に2024年、私の運営する社会福祉法人が公私連携幼保連携型認定こども園を開設します。このこども園の建設にあたっては、本学とも密接に連携し、園庭は本学観光学部の教員が、造園学や園芸療法論の視点でプロデュースします。また、保育士や幼稚園教諭を志す福祉総合学科子ども福祉コースの学生には、どうしたら子どもたちの創造性を伸ばせるのかといったテーマで教室作りのアイデアなどを提案してもらいました。開園後も本学と連携し、同コースだけでなく福祉総合学部理学療法学科や看護学部看護学科の学生の実習や臨床研究の場として、また留学生と子どもたちが触れ合う国際交流のフィールドとして活用していきたいと考えています。
<専門分野・研究テーマ>保育学、児童福祉学、保育思想、保育内容環境、保育マネジメント、食育、食農文化
<キーワード>保育所・幼稚園経営、保育所民営化、保育の質の向上、待機児問題、育児支援、保育所設計、幼児教育、認定こども園、園庭デザイン、食育食農、医療的ケア、障がい児保育、キャリア教育、経営コンサルタント
【外国人移住者】国際人文学部 国際交流学科 教授 林 千賀 「入国制限撤廃で外国籍の子急増 日本語教育の支援急務」
急増する外国人移住者の子どもたちへの日本語教育を支援しています。千葉県山武市では特にスリランカ国籍を持つ住民がコロナ前から倍増しました。日本語ができない子も多く、その対策が急務となっています。昨年3月には同市からの要請で小学校教諭を対象に日本語の指導法を紹介するワークショップを行いました。ゼミの学生たちは、コロナ禍ではできなかった実践学習の場として、昨夏から同市内の小中学校を訪れ、外国籍の子どもたちが楽しく日本語を学べるようにと、カルタや習字などを取り入れた交流会を行い、日本語教育支援に貢献しています。こうした活動も契機となり、今年1月には同市と本学の間で外国人児童生徒の日本語教育支援に係る連携協定も締結されました。外国人移住者は今後も増え続け、支援の必要性は益々高まっていくでしょう。
<専門分野・研究テーマ>日本語教育、第二言語習得論、語用論
<キーワード>日本語教員養成、異文化間コミュニケーション、SDGs
【地域環境保全】経営情報学部 総合経営学科 教授 国武陽子「守れ、里山の希少生物 学生のフィールド教育も再開」
里山に生息する千葉県の最重要保護生物に指定されている両生類「トウキョウサンショウウオ」が山武地域では激減しています。また遺伝的にも固有の集団であることが我々の調査で明らかになりました。急減の原因は耕作放棄による里山の荒廃と外来種による捕食です。農耕文化によって創出された里山は自然と人の共生のモデルと言われています。コロナ禍で屋内に籠りがちな子どもたちにとって貴重な学びの場であり、地域の大切な自然資源です。この春から山武市・東金市の行政機関、市内の小中学校、千葉県農業大学校等と連携し、地域の子どもたちも参加する地域ぐるみの希少種保全活動が開始されます。希少種の保全をきっかけにして、地域の宝である豊かな里山を皆で守り活用する取り組みに積極的に取り組んでいきます。
<専門分野・研究テーマ>生態学、地域生態系保全、生物間相互作用
<キーワード>地域生態系、環境保全、生物多様性、絶滅危惧種、環境教育、里山、トウキョウサンショウウオ
【XR】メディア学部 メディア情報学科 教授 中嶋 正夫 「XR技術、孤立感低減するオンライン授業への活用を模索」
現実世界と仮想世界を融合した画像処理技術「XR(クロスリアリティ)」は、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)の総称で、エンターテイメント分野を中心に活用されてきました。アフターコロナのフェーズでは、このXR技術を教育のツールとして活用し、定着させることを考えています。例えば、教室に360度全天球カメラを設置し、オンライン参加者がゴーグルを着け、対面授業を受けている感覚で受講できるようなメタバース作りなどを模索しています。これにより、オンライン受講での孤立感を低減できます。ただし、長時間ゴーグルを着け続けるのは疲れますので、並行して、肉体的負担を軽減して没入感を得られるような表示方法を検討しています。
<専門分野・研究テーマ>知的教育支援システム、マルチメディア教材、モバイルアプリケーション、人工知能
<キーワード>プログラミング、ゲーム制作、VR、AR、MR、XR、IoT、知的教育支援システム、人工知能、マルチメディア検定
【薬剤師】薬学部 医療薬学科 助教 溝口 優 「増える外国人患者 薬剤師の窓口対応に異変も」
外国人患者にも適切な服薬指導を行える薬剤師向けのツールの開発を進めています。具体的には、薬局で話される数百パターンの会話について、機械翻訳による英語や中国語などへの翻訳精度を調査し、誤翻訳を防ぐための注意事項をまとめたガイドを作成しております。作成したガイドには外国製医薬品の鑑別手順なども併せて記載し、調剤薬局へ無償で配布しています。厚生労働省によると、日本で働く外国人労働者数は、2022年10月時点で182万人余りとなり、過去最多を記録しました。この増加傾向はコロナ後も続き、調剤薬局を訪れる外国人患者もさらに増えると予想されます。我々の作成したガイドが外国人患者の安心につながるツールとして、薬剤師に活用されることを期待しています。
<専門分野>医療薬学、集中治療学
<研究テーマ>医薬品の副作用防止を目的とした臨床研究
<キーワード>グローバル化、国際化、多言語、人種差、ファーマコゲノミクス、薬剤師業務
【観光開発】観光学部 観光学科 教授 多田充 「フィールドワークで町の魅力再発見 地域振興戦略を観光協会に提案」
エコツーリズム、教育ツーリズムなど、自然や農業といった地域環境資源を活用したまちおこし、観光開発に取り組んでいます。昨年は成田国際空港に隣接する千葉県芝山町でフィールドワークを行い、日本人学生や留学生の視点からの観光戦略を同町観光協会に提案しました。こうした活動が評価され、今年3月、同町と本学は包括連携協定を締結し、連携を深めていくことになりました。今年は同町で都内中学校による稲作体験活動を支援し、田んぼを体験学習の場とするプロジェクトを始めます。コロナ後の人流復活をその地域ならではの交流活動、例えば都心と地元の中学生同士や住民とのふれあいに発展させていきたいと考えています。
<専門分野・研究テーマ>環境緑地学、造園学、環境心理学、環境教育学、園芸療法論
<キーワード>自然資源、食農、自然環境の保護と利用創出
【メンタル】看護学部 看護学科 准教授 柚山 香世子 「コロナ禍で失われた触れ合い ドッグセラピーがもたらす効果に注目」
ドッグセラピーは、犬との触れ合いを通した心身のリハビリテーション・治療方法として1970年代に欧米で普及しました。国内の医療施設で専属として働くセラピードッグはまだ少ないのですが、最近は訪問型のドッグセラピーが盛んになってきました。本学では2017年から授業の一環として、地域のNPO法人や児童養護施設、企業と連携しながら、子どもの心のケアとしてのドッグセラピーの効果を検証し、コロナ流行下の3年間も継続してきました。セラピードッグとの関わりによって子どもの感情が穏やかになった事例や人への関心を高める契機となった事例もあります。コロナ禍では外部との接触が減ったことによるメンタルヘルスへの影響がありますが、子どもの傷ついた心を癒すセラピードッグの存在は子どもたちの健康な成長・発達の力を引き出す手立ての一つとなると考えています。
<専門分野・研究テーマ>小児看護学
<キーワード>アニマルセラピー、ドッグセラピー、セラピー犬


.jpg)
.jpg)

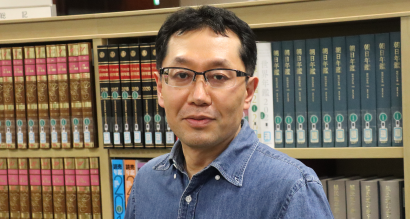
.png)