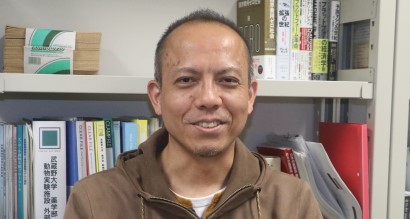Newsletter vol.4 出版物・広報誌
城西国際大学の教育研究活動に関する情報を発信するNewsletter。毎号、全7学部共通のキーワードを軸に研究者たちの多様な取り組みを紹介します。
今月のテーマは【アメリカ考】です。
1776年の独立宣言から2026年で250年となる米国。世界のリーダーとして歴史を紡いできた「自由の国」では今年11月、47代大統領が決まります。混沌とする世界の中の米国の"今"を、全7学部の研究者が国内情勢や文化、暮らし、医療、ビジネス環境など多角的な視点で見つめ、考察します。
- Highlight【大統領選】国際人文学部 国際交流学科 准教授 三島 武之介 「『分断』の先を見越して、日本がなすべきこととは」
- 【文学】国際人文学部 国際文化学科 准教授 大森 夕夏 「複眼的思考と共感から異文化共生の可能性を探る 文化の壁を越えて」
- 【レイシズム】観光学部 観光学科 准教授 柴﨑 小百合 「旅を軸にレイシズム考察─黒人に旅の自由なく 根深い差別意識─」
- 【国際ビジネス】経営情報学部 総合経営学科教授 七井 誠一郎 「グローバル人材育成の土壌に多文化社会 文化や意識収斂世界標準に」
- 【ミュージカル】メディア学部 メディア情報学科 助教 宇田 夏苗 「ミュージカル親しむ環境 求められるリプリゼンテーション」
- 【不妊治療】薬学部 医療薬学科 教授 新倉 雄一 「世界初の不妊治療薬を ボストンでの研究契機に」
- 【心のケア】福祉総合学部 福祉総合学科 教授 佐野 智子 「米国発祥『セルフヘルプ・グループ』難聴支援に応用 『きこえカフェ』の実践」
- 【看護】看護学部 看護学科 教授 北田 素子 「静脈の太さに人種や地域性関連か より安全な輸液ケアの実現へ」
Highlight【大統領選】国際人文学部 国際交流学科 准教授 三島 武之介 「『分断』の先を見越して、日本がなすべきこととは」
2024年米大統領選の状況は、共和党のドナルド・トランプ氏の暗殺未遂、民主党のジョー・バイデン氏の撤退と、目まぐるしく変化しています。しかし、私たちがいま向き合うべき問いは、日本はいかにして米国を導いていくのかです。
常々私は学生たちに、世界秩序のゆくえを決するのは日本だと説いています。かつて世界の「リーダー」だった米国は、価値と文化の分極化がもたらす「政治の衰退」によって国際秩序の不安定要因と化しました。もはや日本は「フォロワー」にとどまれません。私たちには、日本の地政学的位置と政治的安定度などがもたらす独特の国際的地位を自覚し、米国で縮小する国際主義勢力を支えることが求められています。
南北戦争後から第一次大戦にかけての米国では、建国以来の伝統に則り国家の独自性を守ろうとする「古さ」と欧州先進国が取り組んでいた国家改革をとり入れようとする「新しさ」がせめぎ合っていました。ここで大切なのは、「アメリカの世紀」を予期した英国人たちが「新しさ」の効用を説き、それを「フォロー」した米国人たちが「古さ」との両立を図ったことです。この試みは紆余曲折を経ますが、のちに米国は「リベラルな国際秩序」の基盤となるルールや制度を英国から引き継ぐことになります。 昨今、その代表例たる自由貿易体制は少なからぬ米国民に、グローバル化と相まって国内の経済的・社会的格差を広げ、中国の台頭を招いたという印象を与えています。近年の保護主義的な通商政策は、彼らが「新しさ」から「古さ」に目を背けている証左です。一方で、バラク・オバマ政権期に最大勢力として定着した無党派を中心に、新たな政治的選択肢を求める「分断疲れ」が見られます。これは、米国民が「政治の再生」の手がかりを探し求める契機となり得ます。だからこそ私たちは、日本がいかなる「新しさ」を米国に教え諭せるかを考え始めるべきなのです。

三島准教授が論文を投稿した『国際政治』 213号(2024年)
<専門分野>国際政治学、アメリカ政治外交史、グローバル・ヒストリー
<キーワード>国際秩序、国際機構、革新主義、リベラリズム、国際主義、大西洋主義、アメリカニズム、ポピュリズム
【文学】国際人文学部 国際文化学科 准教授 大森 夕夏 「複眼的思考と共感から異文化共生の可能性を探る 文化の壁を越えて」
多文化社会の米国では、個人が複数の文化集団に帰属する形での多様化が進んでいます。個人が、反目する複数の文化集団に帰属意識を持つ場合、その個人は一筋縄ではいかない葛藤を抱えることとなります。このような個人の一人がアフリカ系アメリカ人作家ジュリアス・レスター(1939-2018)です。
公民権運動の際にはアフリカ系アメリカ人の代弁者として、ユダヤ教に改宗した後はユダヤ人擁護の立場から発言を行なったことにより、レスターは想像も及ばないような困難な状況に置かれることとなりますが、その稀有な体験から得た独自の複眼と他者の苦難への共感から、文化の壁を越えて問題の根源を理解するための探求を続けました。分断が深まる米国社会において、異文化集団の苦難への共感が、異文化共生への可能性を切り開くことにつながるのではないかと考えています。

2016年に一般公開された国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館では、アフリカ系アメリカ人の活躍が数多く紹介されている
<専門分野>アメリカのマイノリティ文学
<キーワード>アメリカ文学、ユダヤ系アメリカ文学、黒人文学、異文化理解
【レイシズム】観光学部 観光学科 准教授 柴﨑 小百合 「旅を軸にレイシズム考察─黒人に旅の自由なく 根深い差別意識─」
人種隔離政策の時代、黒人に旅や移動の自由はほとんどありませんでした。映画『グリーンブック』には、黒人旅行者が立ち寄れるモーテルや給油所を探すための案内書The Negro Motorist Green Bookが登場します。黒人お断りで、しばしば暴力で排除しようとした「サンダウンタウン」も各地に点在し、黒人の旅や移動を困難にしていました。そのような町は、深南部の激しい人種差別を逃れるために多くの黒人が移り住んだ北部にこそ多く存在していました。サンダウンタウンは現代にも生き延びているとの研究もあり、レイシズム(人種主義)の根深さを物語っています。
アメリカンドリームを追い求め、旅の自由を享受した白人とは対照的な現実を多くの黒人が生きてきました。これまで研究を重ねてきた「映画におけるレイシズム」の観点から、ロードムービーで、旅とレイシズムの相関を考察するのが今後の課題です。

2017年、米・スペルマン大学で日本におけるレイシズムなどに関して講義した
<専門分野・研究テーマ>文化研究、アメリカ研究、黒人研究
<キーワード>アメリカ映画におけるレイシズムの表象、移動/旅とダイバーシティ、ロードムービーと人種
【国際ビジネス】経営情報学部 総合経営学科 教授 七井 誠一郎 「グローバル人材育成の土壌に多文化社会文化や意識収斂 世界標準に」
日本では「グローバル人材」の確保が叫ばれています。このグローバル人材の確保や育成に関する研究を続けています。英語を話すことができ、多様な文化を吸収、理解できる力を持つ人材で、成長を目指す多くの企業が求めています。
巨大IT企業「GAFA」などを生む米国は、グローバル人材を生み出す土壌が整っていると感じます。多民族・多文化社会だからこそ、世界の文化や意識を国内で収斂していく過程が存在し、ビジネス界でも同様に国際感覚が養われ、グローバル・スタンダードが構築されます。日本企業の成長のためには、このように成り立った世界基準を取り入れていくことが必要ではないかと思います。米国では一般的なインターンシップ採用や職務内容に基づくジョブ型雇用など、企業側の環境を変えることがグローバル人材の育成を促すと考えています。
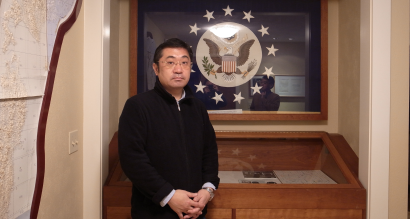
2013年から半年間、ハーバード大エドウィン・O・ライシャワー日本研究所の研究員だった七井教授
<専門分野>国際経営論、国際マーケティング、HRM
<キーワード>世界標準、多文化社会、成田空港南側経済圏の活性化
【ミュージカル】メディア学部 メディア情報学科 助教 宇田 夏苗 「ミュージカル親しむ環境 求められるリプリゼンテーション」
研究はブロードウェイ・ミュージカルを中心としたエンターテインメント文化です。ブロードウェイでは近年「リプリゼンテーション」の考え方が重要視されています。これは、映画やミュージカルなどの分野で、社会の多様性を反映し、公平に描くという考え方で、制作者らはマイノリティに配慮した作品作りが求められます。
米国におけるミュージカルは移民の多様な文化が交わり、大衆の娯楽として確立しました。それゆえに「社会の写し鏡」でもあります。子どもから大人までアマチュアが名作を演じられるよう、正式な台本と楽譜が借りられるシステム、各地に本格的な劇場があるなど、ミュージカルに親しめる環境が整っていることも「リプリゼンテーション」の流れを後押ししていると考えています。

姉妹校のカリフォルニア州立大学ロングビーチ校にも劇場がある
<専門分野>ミュージカル受容史、演劇、エンターテインメントビジネスの変遷
<キーワード>ミュージカル、演劇、多様性、ジェンダー、異文化交流、共感力、アダプテーション
【不妊治療】薬学部 医療薬学科 教授 新倉 雄一 「世界初の不妊治療薬をボストンでの研究契機に」
2022年に創薬ベンチャー「Ovenus(オビナス)」を立ち上げました。起業の発端はバイオベンチャーの拠点、ボストンでの研究です。「卵子の数は出生時に決まり、以後、再生されることはない」というのが生殖医学界の常識でしたが、これを覆す発見がハーバード大の研究チームにより報告されました。この論文に刺激され、翌年の2005年、渡米しました。
6年間に及ぶ米国での研究生活は、世界最先端を走る研究者のポジティブ思考、行動力、そして人を巻き込む力を肌で感じた貴重な体験でした。この恵まれた環境で、老化に伴う卵子再生力の低下を突き止め、それに関わる分子を発見しました。現在は、この分子を標的とした世界初の卵子再生促進薬と卵子再生力を反映した妊娠力診断薬の開発を目指しています。不妊に悩む女性のケアにつながる成果をあげるべく、ビジネス視点を持ちながら研究を推進しています。

米国での研究員時代の新倉教授(右)
<専門分野>分子生物学、細胞生物学、生殖医学
<キーワード>不妊症、流産、更年期障害、卵子、再生医療、アンメット医療ニーズ
【心のケア】福祉総合学部 福祉総合学科 教授 佐野 智子 「米国発祥『セルフヘルプ・グループ』難聴支援に応用 『きこえカフェ』の実践」
難聴者心理の理解と支援に関する研究を行っています。障害者認定を受けられない軽・中等度の難聴者は、公的な支援の対象外です。また、同じ困難を抱える人たちとのネットワークも少なく、悩みを一人で抱え、孤立しがちです。そこで2018年から勝谷紀子氏が主催する難聴者対象の交流会「きこえカフェ」にかかわり、共同研究を行っています。聞こえにくさ、聞き取りにくさを抱える人同士が気持ちや知恵、情報などを共有することが狙いで、すでに50回を越えています。
このようなグループをセルフヘルプ・グループ(SHG)と言います。SHGの起源は1935年に米国で誕生したアルコール依存症のグループと言われています。その後、1960~70年代の市民運動などを背景に、多様なSHGが誕生しました。現在はきこえカフェの機能を社会的役割の視点から検討し、論文化を進めています。
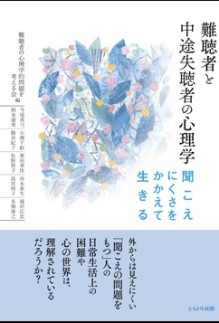
佐野教授らが執筆した共著「難聴者と中途失聴者の心理学 聞こえにくさをかかえて生きる」(難聴者の心理学的問題を考える会 編、2020年、かもがわ出版)
<専門分野>臨床心理学、生涯発達心理学
<キーワード>難聴、コミュニケーション、難聴者の心理の理解と支援、セルフヘルプ・グループ、臨床心理学、トラウマ解消
【看護】看護学部看護学科 教授 北田素子 「静脈の太さに人種や地域性関連かより安全な輸液ケアの実現へ」
米国には静脈内に薬液を投入する輸液ケアを専門に担うInfusion Nurses(輸液看護師)と呼ばれる看護師がいます。また、初期医療や薬の処方が認められたエキスパート職である「Nurse Practitioner(診療看護師)」という職種もあります。このように、看護師の仕事の分業化が進んでおり、日本でもこうした制度の導入が議論されています。
私は輸液に関する研究に力を入れています。昨年5~9月、科研費に採択された研究の一環で、65歳以上の高齢者を対象に、超音波エコーによって静脈の直径を測定する調査を実施しました。平均は1.8ミリでした。研究成果はすでに論文にまとめました。海外の先行研究と比較しても細い結果であり、年齢だけでなく人種や地域性によって静脈の太さが変わるのではないかと考えています。関連を裏付けることはより安全な輸液ケアにつながるため、引き続き研究を進めます。

調査では、超音波エコーで腕の静脈の太さを測った
<専門分野>基礎看護学、看護技術
<キーワード>エコー、末梢静脈カテーテル合併症、熟練看護師、輸液、静脈