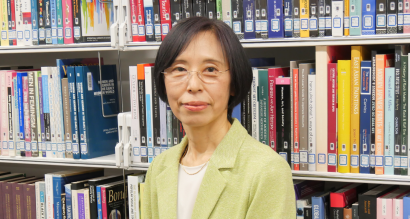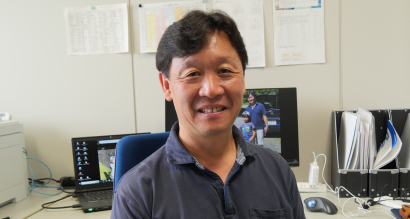Newsletter vol.2 出版物・広報誌
城西国際大学の教育研究活動に関する情報を発信するNewsletter。毎号、全7学部共通のキーワードを軸に研究者たちの多様な取り組みを紹介します。
今号のテーマは【多文化・多様性社会】です。
国籍、民族、言語や年齢、性別・性的指向、思想信条、障がいの有無など、互いの違いを尊重し合い、相互理解しながら共に生きていける「多文化・多様性社会」。その実現のために、いまどのような行動が求められているのでしょうか。7学部9学科を擁する城西国際大学の研究者が、それぞれの専門領域から考察・予測します。
- Highlight【少子化対策】国際人文学部 国際文化学科 教授 魚住 明代 「多世代の家」を軸に家族政策に取り組むドイツの事例から学ぶこと」
- 【HAIKU】国際人文学部 国際交流学科 教授 田 原「五・七・五で「美」を表現 「世界一短い文学」が静かなブーム」
- 【まちづくり】観光学部 観光学科 助教 金子 祐介 「電動車いすの観光利用に着目 究極のスモールモビリティとなるか」
- 【異文化】経営情報学部 総合経営学科 教授 呉 小莉 「日本の文化とコミュニケーションを紹介する、中国人学生向け教科書を発行」
- 【韓流エンタメ】メディア学部 メディア情報 学科 准教授 黄 仙惠 「世界を席巻する韓国コンテンツ 発展を支える人材の成長」
- 【東洋医学】薬学部 医療薬学科 特任教授 地野 充時 「漢方薬のポリファーマシー問題、医師の知識不足も一因か」
- 【高齢社会】福祉総合学部 福祉総合学科 助教 茆 海燕 「IT化進む中国の介護 日本はサービスの質で先行」
- 【ストレッチ】福祉総合学部 理学療法学科 助教 深谷 泰山 「短時間・強負荷でリハビリ効果向上 VR使用のシステム開発も」
- 【看護の国際化】看護学部 看護学科 助教 石井 恵美子 「一人ひとりの状況に即した適切なケアの担い手を育成」
Highlight【少子化対策】国際人文学部 国際文化学科 教授 魚住 明代 「「多世代の家」を軸に家族政策に取り組むドイツの事例から学ぶこと」
日本同様に低出生率や高齢化といった人口問題に直面しているドイツの状況について、2018年から地域における家族政策に焦点を当てて調査を行っています。
かつてドイツでも、女性は家庭に活動の重点を置く生活スタイルが一般的でした。しかし、メルケル首相が就任した2005年頃から、女性も外で働き、男性も育児休暇を取るなど、政策の掲げる家族モデルが変化してきました。
ドイツ政府は様々な家族政策を講じています。その中でも特筆すべきなのが、地方自治体への資金援助の一環として2006年から各地に開設された連邦プログラム「多世代の家」です。子どもから高齢者まで利用できる公民館のような交流型施設で、幅広い世代が相互に助け合いながら交流しています。運営を支えるのは、福祉支援団体や地元企業、地域住民のボランティアです。
現在「多世代の家」は全国約530カ所に設置され、料理や工作などの教室やカフェ、人生相談、祭りなども展開しています。出産後の母親を対象とした体操教室では、参加者の赤ちゃんの面倒を高齢者が見ることも。また、地元住民と移民とが言語を相互学習する機 会も設けられています。育児や就業をサポートしたり、高齢者の孤立を防いだりという役割を果たしている「多世代の家」が、人口問題解決の一翼を担う存在にもなっているのです。
公益財団法人アーバンハウジングからの委託研究で「多世代の家」を1年間にわたって調査した結果、利用者の相互理解を促進し、仕事と子育て・介護の両立を支援するとともに、地域住民の経済的負担を軽減する効果をもたらしていることも確認できました。
若者も高齢者も地域活動に参加できるような社会システムを構築することで、全国レベルでの地域活性化を図る「多世代の家」。少子化が急速に進む日本でも、参考になる取り組みと言えるでしょう。調査は一旦終えて報告書にまとめましたが、今後は、現在第4期に入った本連邦プログラムの成果と課題を、専門家への聞き取りも踏まえて掘り下げたいと考えています。
<専門分野・研究テーマ>家族社会学、ドイツ研究、ジェンダー論
<キーワード>ドイツの家族制度
【HAIKU】国際人文学部 国際交流学科 教授 田 原(デン ゲン)「五・七・五で「美」を表現 「世界一短い文学」が静かなブーム」
1991年に国費留学で中国から来日後、詩人として活動するほか、日本の詩や小説を多数、中国語に翻訳してきました。特に谷川俊太郎、金子みすゞ、松尾芭蕉、太宰治の作品を「外からの目線」でとらえた翻訳は中国で大きな反響を呼びました。また、後世に残したい日本の俳句として1,310句を私なりの視点で選び、一冊にまとめた名句選も発表しています。近年、SNSで短文投稿に親しんだZ世代の間でも、俳句が静かなブームとなっています。海外でも「世界一短い文学」として「HAIKU」(自由律俳句)愛好家が増えています。コロナ下での孤立もあって、みんな自分を表現したがっているのではないでしょうか。読後の余韻に重点が置かれ、17音で「美」を最大限に表現する俳句は、日本人の精神性が宿った、いわば「日本の宝」と言えます。これからも中国、そして世界に、その魅力を伝えていきます。
<専門分野・研究テーマ>日本現代詩(谷川俊太郎を中心に研究・翻訳)
<キーワード>谷川俊太郎、日本現代詩、俳句
【まちづくり】観光学部 観光学科 助教 金子 祐介 「電動車いすの観光利用に着目 究極のスモールモビリティとなるか」
健常者における電動車いすの観光利用の可能性を探る実証実験を、2022年から企業の協力のもとで行っています。電動車いすは障がいの有無にかかわらず、楽に移動でき、体力を温存しながら活動範囲を広げることができるスモールモビリティとも言えます。実証実験は、北海道上士幌町などの自治体にご支援いただき、事業を進めてきました。ゼミ生たちは、この町のほか横浜市や新潟県上越市などに出向き、実際に電動車いすに乗って地域を回っては、各地域の歩道走行上の課題や、自動運転バスや無人のコンビニといった未来社会の変革に対応する際の課題の整理などについて、約3年間にわたって記録を取り、課題の可視化を実践してきました。走行上起こり得る安全面の問題や、レンタル施設などの不足といった課題もありますが、電動車いすは観光地での移動手段を変えるポテンシャルが十分にあると考えています。
<専門分野・研究テーマ>地域ブランディング、まちづくり、アーバンデザイン論、建築・デザイン史
<キーワード>地域社会、住民参加型まちづくり、地域基盤整備、地域資源
【異文化】経営情報学部 総合経営学科 教授 呉 小莉 「日本の文化とコミュニケーションを紹介する、中国人学生向け教科書を発行」
1990年に中国から来日以来、本学で中国人留学生に日本語を、日本人学生に中国語と国際語としての英語を教えてきました。その経験をもとに昨年、中国の大学で日本語を専攻する学生を対象とした教科書を出版しました。日本人とのコミュニケーションを理論だけではなく実践的に学ぶもので、国民性による行動の違いや、寛容、礼儀正しさといった日本独自の文化や慣習、さらにはコミュニケーションスタイルなども紹介しています。私が執筆に関わった(共著)教科書で学ぶ中国の大学生、また私が現在直接教えている日本の学生には、国際的なコミュニケーション能力を高め、異なる文化を尊重する姿勢を培ってもらいたいと願っています。またその力を社会に出てからも発揮し、異文化間の交流を促す人材になってくれることを期待しています。
<専門分野・研究テーマ>異文化コミュニケーション学、第二言語習得研究
<キーワード>異文化コミュニケーション教育、異文化コミュニケーション著書の翻訳
【韓流エンタメ】メディア学部 メディア情報 学科 准教授 黄 仙惠 「世界を席巻する韓国コンテンツ 発展を支える人材の成長」
2003年のドラマ「冬のソナタ」の大ヒットに端を発した韓流ブームの後押しで、韓国のコンテンツビジネスは大きく発展しました。ドラマ、映画、音楽、アニメーション、漫画といったコンテンツの生産のみならず、マネジメント、ファンコミュニティの運営、イベントの開催、日本での拠点づくりといったエンタテイメントビジネスへと進化していきました。こうしたビジネスの現場でコンテンツプロデューサーとして、制作や流通、マネジメントを通じた日韓間の大衆文化の橋渡し役を担ってきました。また、教鞭を執る傍ら、コンテンツの日韓共同制作なども進めています。韓国のコンテンツ産業が発展し続けている要因の一つは、人材の成長です。失敗を恐れず次々とアイデアを出して行動する人材が育っています。日本の学生にもそうした人材に育ってほしいと願い、授業ではノウハウだけでなくマインドの大切さについても語っています。
<専門分野・研究テーマ>メディアデザイン学、韓流エンタテイメント
<キーワード>メディアデザイン、コンテンツビジネス、エンタテインメントビジネス、韓流、韓国メディア
【東洋医学】薬学部 医療薬学科 特任教授 地野 充時 「漢方薬のポリファーマシー問題、医師の知識不足も一因か」
漢方薬のポリファーマシー(併用処方)による健康被害を危惧しています。漢方専門医は、様々な症状に対し、患者さんの病態を表す「証(しょう)」を見極め、適切な漢方薬を選択します。しかし、漢方薬に詳しくない医師は、あたかも西洋医学で症状ごとに「1対1」で薬を処方するように漢方薬を処方します。そのため別々の医療機関に所属する複数の医師が、一人の患者さんに複数の漢方薬を処方してしまうという現象が起きています。漢方医学教育がコア・カリキュラムに盛り込まれたのは2001年からと歴史が浅く、医師の知識不足もその一因と考えられます。日本東洋医学会などとも連携し、こうした現状を改善するための啓発活動などを続けることで、「東」と「西」それぞれの強みを活かした治療効果が得られるよう努めています。
<専門分野・研究テーマ>和漢診療学、内科学
<キーワード>現代医療における漢方薬の臨床応用、ポリファーマシー、漢方薬、東洋医学
【高齢社会】福祉総合学部 福祉総合学科 助教 茆 海燕 「IT化進む中国の介護 日本はサービスの質で先行」
日中間の高齢者介護の相違点に着目しています。中国も「高齢社会」に突入しました。政府はIT技術を活用した介護に力を入れ、通院する在宅患者のバイタルデータを24時間モニタリングする病院も出てきました。一方、高齢化が世界で最も進む日本は、介護保険制度をベースとした手厚いケアと質の高いサービス、介護施設の行き届いた管理などの分野で先行し、中国企業からも注目されています。本学科には中国人留学生も多く、卒業後は母国の介護施設経営者になることを目指して、日本の福祉・介護を学んでいます。留学生と日本の学生が互いの国の福祉・介護を学び、両国の社会課題の解決に何ができるのかを日々模索し合えるよう、サポートしています。
<専門分野・研究テーマ>社会福祉学、日中高齢者福祉論
<キーワード>中国農村部における地域高齢者への支援システム
【ストレッチ】福祉総合学部 理学療法学科 助教 深谷 泰山 「短時間・強負荷でリハビリ効果向上 VR使用のシステム開発も」
ストレッチの効果について研究しています。専門の器具を使ってストレッチ前後の筋肉の硬さを測定・比較したところ、ストレッチ運動は、年齢にあまり関係なく長い時間をかけて弱い力で行うよりも、短い時間で強く行ったほうが、効果が高いという実験結果が得られました。しかし、強いストレッチ運動は痛みや不快感を生じる可能性があり、本来の正しい運動が行えないケースが多々見受けられます。そこで現在、VR(仮想現実)技術を利用し、リラックス効果のある映像やサウンドをゴーグルやヘッドフォンで視聴しながら、どんな世代でもより効果的にストレッチ運動ができるようにVR関連の企業とともに取り組んでいるところです。来年度にはこの研究で科研費にも申請をする予定です。
<専門分野>ストレッチングが柔軟性に及ぼす効果、基礎理学療法
<キーワード>ストレッチング、柔軟性、超音波画像診断装置
【看護の国際化】看護学部 看護学科 助教 石井 恵美子 「一人ひとりの状況に即した適切なケアの担い手を育成」
医療現場で国際的な環境にも適応できるようにと、看護学部生の演習に他学部の留学生にも模擬患者として参加してもらう試みを2021年から実施しています。「やさしい日本語」を心がけながら留学生とコミュニケーションをとるなかで、最後は国籍に関係なく、患者さんの個性を理解し尊重する意識が大切であることを学びます。留学生も、看護学部生との交流や模擬患者としての役割体験を通じて充実感や満足感を得ることができ、日本語学習への意欲向上にもつながっているそうです。卒業後、多様な患者さんに迅速かつ適切なケアを提供できる看護職者を育成することが目標です。この演習に参加した卒業生の一人は、助産師として就職後「海外で医療に携わりたい」と一念発起してJICA海外協力隊に応募し、2024年から助産師としてタンザニアへ派遣される予定です。この演習で学んだ学生が、世界各地で活躍することを期待しています。
<専門分野・研究テーマ>母性看護学、在住外国人の母子保健、協働学習
<キーワード>国際看護