
Newsletter vol.3 出版物・広報誌
城西国際大学の教育研究活動に関する情報を発信するNewsletter。毎号、全7学部共通のキーワードを軸に研究者たちの多様な取り組みを紹介します。
今号のテーマは【ウェルビーイング】です。
身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念が「ウェルビーイング」。その実現のために、いまどのような行動や社会の仕組みが求められているのでしょうか。7学部9学科、そして教養教育を担う各種センターを擁する城西国際大学の研究者が、それぞれの専門領域から考察・予測します。
- Highlight【多死社会】看護学部 看護学科 教授 二宮 彩子 「ニーズ高まる高齢者の在宅看取り カギ握るヘルパーの教育プログラム開発へ」
- 【伝統教育】国際人文学部 国際交流学科教授 井上 敏昭「コミュニティ全体の幸福という視点 示唆に富むアラスカ先住民の実践例」
- 【働き方】観光学部 観光学科 教授 長谷川 正人 「地域活性化のカギを握るワーケーション集客」
- 【香り】経営情報学部 総合経営学科 助教 中村 智香 「危険運転防止などにも一役 社会課題解決に活用進むアロマテラピー」
- 【美術教育】メディア学部 メディア情報学科 准教授 高桑 真恵 「造形力高めるコツは動物の構造理解 解剖学取り入れた人体クロッキー」
- 【薬クライシス】薬学部 医療薬学科 教授 小林 江梨子 「後発医薬品の安定供給に黄色信号 製薬業界の産業構造に課題も」
- 【超高齢社会】福祉総合学部 福祉総合学科 准教授 林 和歌子 「一律的な高齢者支援からの脱却を 地域と連携した支援のあり方模索」
- 【テクノロジー】福祉総合学部 理学療法学科 教授 大西 忠輔 「3Dプリンター用いた足底装具開発 高齢者悩ます変形性膝関節症の予防へ」
- 【ハラスメント】語学教育センター 助教 トリシア・アビゲイル・サントス・フェルミン 「外国人英語指導助手、志半ばで帰国も 校内でのハラスメント被害が発覚」
Highlight【多死社会】看護学部 看護学科 教授 二宮 彩子 「ニーズ高まる高齢者の在宅看取り カギ握るヘルパーの教育プログラム開発へ」
どこで、人生の最期を迎えたいか?内閣府の「令和元年版高齢社会白書」によると、60歳以上の5割を超える方が「自宅」と答えています。しかし実際に在宅で看取られる方は2割にも満たないのが現状です。
「在宅で看取るのは無理」と考える方も多いと思いますが、本当にそうでしょうか。その考えの根底には「病院のほうができる限りのことをしてもらえる」との考え方、そして経験したことのない「死への恐怖」があります。しかし、人が寿命を迎えてゆっくりと死に臨するとき、生理学的には本人が望む以上の水分や栄養の積極的投与はすべきではないとされています。つまり、特別な医療行為や新たな機器の装着等をせず、穏やかな在宅での看取りは十分に可能なのです。
在宅看取りを実現するには、やはり専門職である介護職(ヘルパー)によるケアが大きな役割を果たします。しかしながら、我々が実施した、全国の訪問介護事業所を対象とした調査では、ヘルパーの「看取りに対する自信の無さ」が明らかになりました。そこで、人々が希望通り自宅で最期を迎えてもらうために、ヘルパーが自信を持って不安なく在宅看取りケアに向き合えることを目的とした、教育プログラムの策定に取り組んでいます。
生と死は切り離せるものではありません。人は死ぬ直前までより良く生き、より良く死ぬ権利があります。介護する側、される側の両者がより良く生きることのできる、そして望んだ状態で最期を迎えることのできる社会の構築に向けて研究を進めています。
<専門分野>基礎看護学、看護管理
<キーワード>在宅看取り、在宅療養者の鬱症状など
【伝統教育】国際人文学部 国際交流学科 教授 井上 敏昭 「コミュニティ全体の幸福という視点 示唆に富むアラスカ先住民の実践例」
日本ではウェルビーイング(WB)を個人単位で考える傾向にありますが、コミュニティが良い状態かといった視点も含めてWBを捉える必要があると考えています。30年ほど前から私が研究対象としているアラスカ先住民集落では、地域全体がどうしたら幸せになるかを考えています。そのために実践していることの一つが、親以外の大人が子どもを教え導く伝統的な教育です。子どもたちは、狩りは狩りの名手に、漁は漁の名手に一対一で教わりながら、技術や知識だけでなく社会でのふるまい方、世界観や価値観を学んでいきます。子どもが親や教師以外の大人と関わらなくなった日本でも、先住民に学ぶことが多いのではないでしょうか。
<専門分野>文化人類学、極北先住民研究
<キーワード>マイノリティ、食文化、贈与論、開発と環境、伝統の継承
【働き方】観光学部 観光学科 教授 長谷川 正人 「地域活性化のカギを握るワーケーション集客」
コロナ流行下で注目度が高まった働き方が「ワーケーション」です。移住による人口増にもつながることから、さまざまな自治体がワ―ケーションの誘致に乗り出しています。数ある候補先から選択してもらうには何をすべきなのか。私のゼミでは千葉県館山市にご協力をいただき、学生たちが現地調査や実際にワーケーションをしている方にインタビューを行い、同市に対して提言を行いました。同市が持つ魅力の掘り起こし、リピーターにつながる地域住民との関係性づくり、テレワークをスムーズに行うためのセミナーの実施、インフラの整備、SNSを活用した情報発信など、学生たちは多岐にわたる実現可能な提言を行いました。
<専門分野・研究テーマ>航空ビジネス戦略に関わる研究、地域活性化に関わる研究、働き方改革と旅の効用に関わる研究
<キーワード>エアラインビジネス、地域活性化、働き方改革
【香り】経営情報学部 総合経営学科 助教 中村 智香 「危険運転防止などにも一役 社会課題解決に活用進むアロマテラピー」
アロマテラピーの心身に与える効果が実証され、医療・介護分野においても広く使われるようになってきました。例えば、認知症患者に午前中にはすっきりした香り、夕方にはリラックスする香りを嗅いでもらうと、認知機能の改善がみられることがわかっており、一部の高齢者施設ですでに取り入れられています。映画館などエンターテイメント分野での活用や、危険運転を防止する香りの研究なども進んでいます。香り・においの力で社会をより良くすることができる。この仮説のもと、今後は健康やスポーツ、出産・子育て分野、具体的には出産前後の母親のストレス軽減や子どもの心の成長に、香りがどのような効果をもたらすのか、その可能性を探る研究を進めていきたいと考えています。
<専門分野>香り・におい、薬学
<キーワード>健康維持、香育、医療や福祉、企業ブランディング、販売促進、空間演出、VRやデジタル分野など、幅広い領域での香り・においの活用についての検討
【美術教育】メディア学部メディア情報学科 准教授 高桑 真恵 「造形力高めるコツは動物の構造理解 解剖学取り入れた人体クロッキー」
メディア学部にはアニメーターやCGクリエイターを目指す学生も多くいます。こうした職業に就くには一定以上の造形力を要しますが、本学は美大ではないため、入学前に絵の勉強をしている学生はほとんどいません。そこで私の授業では造形力を高めるトレーニングを行っています。人や動物を描くときに重要なのは、解剖学です。表層からは見えない、骨格や筋肉、その動きを想像して描くことでリアリティが生まれます。この解剖学を取り入れた人体クロッキー(速写)の手法は、絵を学ぶ美術学生の間で「高桑式」とも呼ばれ、拙著が美大の教科書としても使われています。授業では2~3分ごとにポーズを変えるモデルを見ながら、60枚ほどのクロッキーをどんどん描いてもらいます。その横で私が骨や筋肉についての解説をし続けます。そしてヒトを基本形と捉え、他の動物の構造を理解することで、学生の造形力は見違えるほど向上し、クリーチャーモデリング等にも役立ちます。
<専門分野>美術解剖学、芸術実践論、アニメ、コンピューターグラフィックス
<キーワード>人体クロッキー、美術解剖学、デジタル彫刻、クリーチャーモデリング
【薬クライシス】薬学部 医療薬学科 教授 小林 江梨子 「後発医薬品の安定供給に黄色信号 製薬業界の産業構造に課題も」
臨床現場で後発医薬品(ジェネリック医薬品)の占める割合は約8割に及びますが、その安定供給がいま危機に瀕しています。昨年末の風邪薬不足は皆さんも記憶に新しいのではないでしょうか。もちろん品質問題も要因としてあるのですが、後発医薬品を作っている多くの製薬会社が少量多品目の生産体制であることも一因となっています。1つの薬を20社以上が作っている例もあり、これが“買い叩き”にもつながっています。私は現在、厚生労働科学研究「適切な医薬品開発環境・安定供給及び流通環境の維持・向上に関する研究」に参画し、少量多品目構造の解消、薬価の安定に向けた企業情報の可視化などについて検討を行っています。
<専門分野>医療行政、薬事規制、医療に与える社会的要因
<キーワード>医療用医薬品、医療保険制度、薬価制度
【超高齢社会】福祉総合学部 福祉総合学科 准教授 林 和歌子「一律的な高齢者支援からの脱却を 地域と連携した支援のあり方模索」
65歳以上が高齢者、75歳以上が後期高齢者と定義されていますが、その年になったら突然老いがやってくるわけではありません。人によって必要な支援は異なり、時間の経過によっても変わります。また本来、介護保険は自分で契約を結び、必要なサービスを選択する制度なのですが、施設でのサービスの実態は集団生活を中心とした一律的な支援にとどまっています。
2025年には、約700万人いる団塊の世代(1947~49年生)が後期高齢者となります。自分らしく自由な生活スタイルを維持したい、大型の施設で行われているような画一的な支援は受けたくない、と考える層が今後益々増えると思われます。個性豊かでこだわりのある高齢者を地域が中心となってこれからどう支援していくのか。ゼミの学生とともに、研究を進めています。
<専門分野>高齢者福祉,社会福祉援助技術論
<キーワード>高齢者の自己決定、外国人介護人材、介護実習評価
【テクノロジー】福祉総合学部 理学療法学科 教授 大西 忠輔 「3Dプリンター用いた足底装具開発 高齢者悩ます変形性膝関節症の予防へ」
高齢者が要介護となってしまう主な原因として「変形性膝関節症」が挙げられます。この疾患は膝関節軟骨の老化などが原因で発症するもので、高齢になるほど罹患率が高まり、進行すると歩行が困難になります。治療としては、リハビリテーション、装具療法、薬物療法といった保存療法が主軸となります。
私の研究では、その保存療法の中でも骨格アライメント(骨や関節の並び方)にアプローチする装具療法に着目しています。足底装具(インソール)自体は伝統的に治療に使用されていますが、私はこれまでのものに対して、品質が安定していて大幅な製作時間の短縮にもつながる、3Dプリンターを用いた足底装具の開発を進めています。本研究で開発した装具装着による予防モデルが提示できれば、医療費や介護費の増大など、超高齢社会の日本が抱える課題を解決する一助にもなると考えています。
<専門分野>義肢装具学、人間医工学(生体医工学)、ヘルスプロモーション
<キーワード>身体アライメント評価、ヘルスプロモーション、装具と運動療法の併用
【ハラスメント】語学教育センター 助教 トリシア・アビゲイル・サントス・フェルミン 「外国人英語指導助手、志半ばで帰国も 校内でのハラスメント被害が発覚」
中学・高校の英語教育で日本人教員とチームティーチングを行うフィリピン人の外国語指導助手に対し、学校内でハラスメントが横行している事例が少なからずあることが私の調査で明らかになりました。上司・同僚からの暴言や無視といったパワハラ・モラハラに加え、生徒からの性的ないやがらせ発言など、内容は多岐にわたります。外国語指導助手に関する過去の調査を参照して、精神的ショックから帰国してしまった元指導助手に話を聞くと、文化の違いによる誤解や国籍差別からハラスメントに発展しているケースが多いことがわかりました。
日本は現在、多様性のある教育環境づくりを推進していますが、逆にその多様性が軋轢を生むケースもあります。文化的な背景や国籍に関係なく、その場に集う教員がみんな気持ちよく働ける環境を作るためにはどうするべきか、調査と分析を進めています。
<専門分野・研究テーマ>日本における外国語指導助手の研究、外国人労働者に対するハラスメント問題、ポピュラーカルチャーとジェンダー
<研究テーマ>ジェンダーとセクシュアリティ、教育社会学、文化社会学、日本研究





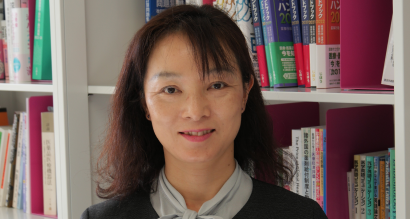

.png)
